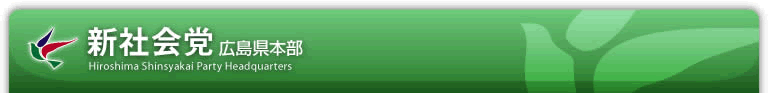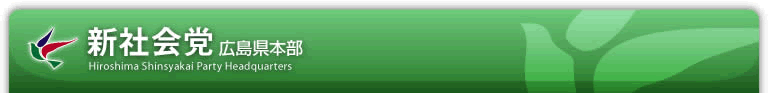|
|
|
07.【1月号】社会主義の歩みと将来への展望 31
|
|
2007/01/09
|
〈社会主義の歩みと将来への展望〉
個人の尊厳と自立的連帯を求めて
広島大学名誉教授 北西 允
第31回 スペイン人民戦線政府の樹立と内戦、そして敗北
第一次世界大戦後、スペインでは左右両派の対立が激しく、その上カタルニアやバスク地方では独立の動きもあって政局は混迷を続けた。一時は軍事独裁政権が誕生するが、1931年には左派が選挙で勝利し王制は共和制に取って替わられた(スペイン革命)。その後1933年の選挙で右派が一旦政権を奪還したものの、1936年の選挙で左派が再び勝利を収め、共和主義左派のM.アサーニャ(1880〜1940 )を首班とする人民戦線政府が樹立された。これに参画したのは、共和主義左派、社会党、共産党、マルクス主義統一労働者党等の諸勢力であった。
選挙によつて成立した人民戦線政府に対し、モロッコ派遣軍のF.フランコ(1892〜1975 )が間もなく軍事反乱を起こし、政府軍はこれを迎え撃った。そのためスペイン全土が次第に血なまぐさい戦場と化していった。ヒトラーのナチス・ドイツ、ムッソリーニのファシスト・イタリアは、叛乱軍を全面的かつ積極的にバックアップした。また、A.サラザール(1889 〜1970 )の独裁政権下にあったポルトガルもフランコを支持した。(1937 年4月、独伊両空軍のバスク地方の都市・ゲル二カに対する無差別爆撃は、それに抗議して描いたピカソの代表作「ゲル二カ」で知られる。)
一方、人民戦線内部では、トロツキストやアナキストと共産党の間で紛争が絶えなかった。社会主義革命戦争の遂行を主張する前者と反ファッショ民主主義擁護に徹すべきだとする後者の対立がそれである。ソ連は人民戦線政府を支援し、当初は人民戦線内部で劣勢だつた共産党が次第に力を増していった。コミンテルンの肝煎りで主に各国の共産党員から成る国際義勇軍(E.ヘミングウェイ、A.マルローらも参加)が編成されたが、ここでも内紛が絶えず、政府軍の拠点の一つであったバルセロナでは干戈を交えるまでに至った(G.オーウェルは、共産党批判の立場から『カタルニア賛歌』を書いた)。フランス人民戦線政府は、最初はスペイン政府軍を支援したが、ほどなくイギリス・アメリカとともに中立的立場をとるようになった。因みに、ローマ法王は早くからフランコに肩入れし、メキシコ政府は終始スペイン政府を支持した。
ドイツ・イタリアによる大量の軍事支援を得た叛乱軍は、圧倒的な軍事力で政府軍の拠点を徐々に制圧し、1939年2月遂にマドリードを攻略して勝利を決定づけた。ファランヘ党党首にも就任していたフランコは、以後1975年の死に至るまでファッショ的独裁政権を維持し続けることになる。
|
|
|
|
|