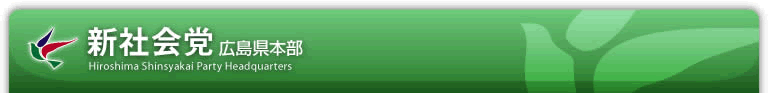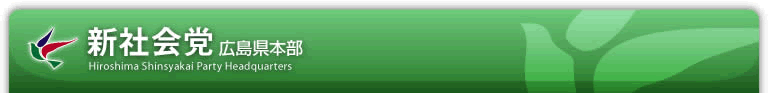|
|
|
【3月号】第33回 スターリン体制下のソ連
|
|
2007/03/13
|
社会主義の歩みと将来への展望
個人の尊厳と自立的連帯を求めて(33 )
広島大学名誉教授 北西允
第33回 スターリン体制下のソ連
左派(トロツキー)右派(ブハーリン)のライバルを屠ったスターリンは、自らをマルクス及びレーニンの政党後継者に任じ、「マルクス・レーニン主義」なるものを唱導して、自らを含む個人崇拝の気運を醸成した。彼は、民主集中制の党組織原則を一層強化し、一切の分析、すべての異論を容認しなかった。こうした体制は、単にソ連内部にとどまらず、コミンテルンを通じて各国共産党にも普及した。
それにも拘わらず、スターリンは、1936年に新憲法(スターリン憲法として知られる)
を制定し、プロレタリア民主主義の発展と労働者の幅広い権利の保障を盛り込んでみせた。そのことは、ソ連が1930年に世界を揺るがした大恐慌の影響をなんら受けることなく、5カ年計画の推進によって大きな経済成長を遂げたことあいまって、資本主義諸国の社会主義者の一部からも高い評価を受けた。反マルクス主義の立場を貫いてきたフェビアン社会主義の創始者の一人であり、劇作家としても名高いG.バーナード・ショー(1856〜1950 )でさえ、この時期のソ連を「失業も階級もない理想の国」と讃えたほどである。
スターリンによる一国社会主義体制は、数百万人とも数千万人とも言われる犠牲者を出す一方、ロシアが長年にわたって引きずってきた富の偏在に大鉈を振るい、絶対的貧困の解消や公衆衛生の改善などの社会政策面で一定の成果をあげた。後に日本社会党の江田三郎が「新しい社会主義のビジョン」の一つに挙げた「ソ連の充実した社会保障制度」には確かに見習うべきものがあった。学校教育はすべて無償で、公共料金なども低く抑えられた。
ところでソ連は、革命当初から内外の脅威にさらされてきた。自衛軍との内戦、外国からの干渉戦争。日本もシベリアに出兵し最も長くかの地にとどまった。レーニンやトロツキーらが期待した社会主義革命の他国への波及は阻止されたが、スターリンは一国社会主義の実現の可能性を主張して、自己の絶対的支配下に国力の充実と外的への備えに専念した。
1935年におけるコミンテルンの反ファッショ統一戦線戦術の採択も、大義である世界革命という能動的立場ではなく、「社会主義の砦」ソ連の防衛という受動的姿勢に立脚していた。独ソ不可侵条約(1939年)という世界を驚かせた奇策も、こうした観点から打ち出されたのであった。
|
|
|
|
|