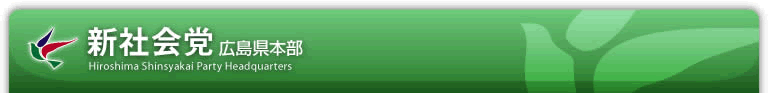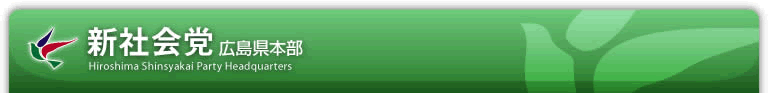|
|
|
7月号】社会主義の歩みと将来への展望第37回
|
|
2007/07/12
|
社会主義の歩みと将来への展望
第37回 コミンテルンと異なる毛沢東の抗日戦略
広島大学名誉教授 北西 允
1936年末の西安事件を契機に、翌37年9月には、国民党総統の蒋介石と西安入りした共産党代表の周恩来(1898-1976)の間でようやく「抗日民族統一戦線」の結合が合意された。それまで蒋は、日本軍の侵攻に消極的には抵抗しつつも、国内の敵・共産党軍の党伐に重点を置いてきた(先安内後攘外)。しかし第2次国共合作の成立によって国共間の10年に及ぶ内戦は収束に向かい、同年9月に北方の共産党軍(紅軍)は国民革命軍第八路軍(八路軍)と改称して蒋の統率下に入り、10月には南方でも各地で活動していた紅軍遊撃隊を結集して国民革命軍新編第四軍(新四軍)が編成された。こうして抗日統一戦線は、名実ともに一応の完成を見た。
時あたかも日本軍は、1937年7月の廬溝橋事件を口実に、「満州事変」の場合と同様、軍が独断専行し政府がそれを追認するという形で中国に対する全面侵略に乗り出していた。日本軍は華北では天津・北京を占領する一方、8月には上海でも新たな戦端を開き、12月には首都・北京を攻略するに至った。この時、日本軍は30万人以上とも言われるおびただしい数の中国人を虐殺し、世界中から激しい非難を浴びたことは周知である(南京虐殺事件)。
この間、1万5千キロに及ぶ長征途上の遵義会議(1935年)で、毛沢東は、都市プロレタリアの蜂起に固執するコミンテルン派に対して農民に依拠する長期革命路線を力説し、党内の指導権をほぼ手中に収めた。その後、毛は根拠地・延安にあって抗日戦を指導する傍ら、『矛盾論』『実践論』(1937)を発表して自らの革命路線を定式化した。
しかし、共産党内には抗日戦を巡ってなお意見の対立が残っていた。コミンテルン中国代表部の王明らは、英・米・ソなどの国際的支援を期待して、蒋介石統一指導下の国民党軍による短期決戦を唱えたのに対し、蒋に信を置かなかった毛沢東らの中国共産党幹部は、国民党軍は抗日戦の主体にはなり得ないとして、コミンテルンの方針に反し、八路軍、新四軍を主力とする時久的遊撃戦論(毛『抗日遊撃戦争の戦略問題』1939年)を主張した。
蒋は日本軍の南京攻略に先立ち武漢、さらには重慶へ首都を移転した。一方、日本軍は南京攻略の翌年10月には武漢三鎮、広州を占領する一方、重慶に対する国際法違反の無差別爆撃を強行し続けた(38年−43年)。だが日本軍は点と線を確保したに過ぎず、戦線は膠着状態に陥り、コミンテルンの短期決戦論は現実によって破綻を証明されたのである。
|
|
|
|
|