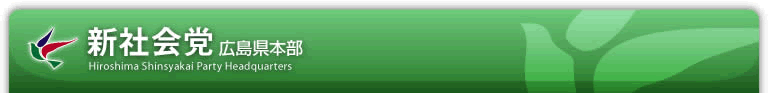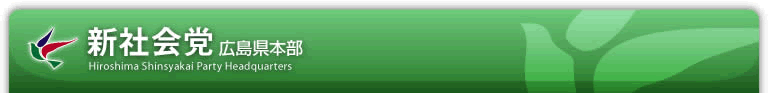|
|
|
【8月号】社会主義の歩みと将来への展望38
|
|
2007/08/30
|
第38回 社会大衆党の結成と大政翼賛会への 合流
先述したように、日本における戦前の無産政党(「無産政党」という用語は、共産党を除く社会主義政党全体の呼称として一般に使われた)は、結成当初から政府・官憲の厳しい監視と激しい弾圧のもと、離合集散や党派間闘争に明け暮れ、社会の変革はおろか国政に影響を及ぼすだけの力量を培うことさえできなかった。それどころか、日本帝国主義の中国侵略がエスカレートするに伴い、無産政党は、やがて軍部や革新官僚(安倍晋三の祖父・岸信介はその代表者のひとり。「革新」とは、当時世界大恐慌の埒外にあって5ヵ年計画を強力に推進していたソ連を参考に国家主義的統制経済を目指したところから来る)に迎合する姿勢を強めていった。
1931年には労働農民党、全国大衆党と社会民衆党の一部が合同して全国労農大衆党が結党され、さらに翌32年には全国労農大衆党と社会民衆党が合同して社会大衆党が結成された。これによって無産政党の統一が実現し、委員長には安部磯雄(1865-1949)、書記長には麻生久(1891-1941)が就任した。
しかし麻生はじめ党幹部の中には、資本主義を変革する主体として、労働者と青年将校の結合に期待するものも多く、党の姿勢はますます国家社会主義的方向に傾いていった。
廬溝橋事件を契機に日中戦争が本格化した1937年の総選挙で、社会大衆党は37議席を獲得するが、これによって自信を深めた党指導部は、むしろ一層軍部への接近を強めた。社会大衆党は、日本軍の中国侵略を積極的に支持し、文部省編纂の『国体の本義』に沿って綱領を改定し、挙国一致体制への参画を公然と表明するに至った。同党は、近衛首相が1938年、帝国議会に提出した国家総動員法案に積極的に賛成したが、同法は、政府に広範な委任立法権を付与して議会の機能を無力化し、政党の比重を全体として著しく低下させる内容の法律であった。
さらに第2次近衛内閣は、かねてから計画されていたファッショ的新体制運動を本格化させ、1940年10月には一国一党を目指す大政翼賛会を結成した。社会大衆党は、すでにこれに先立つて解党していたが、続いて他党もそれぞれ解党してこれに合流し、ここに明治時代以来の日本政党史の幕は一旦閉じられたのであった。
|
|
|
|
|