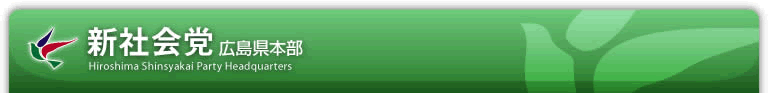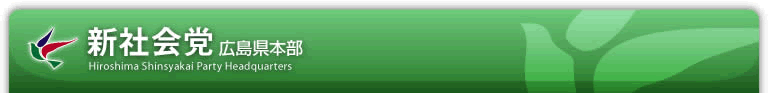|
|
|
【9.10月号】時言1「戦後レジュームの子という自覚」
|
|
2007/10/23
|
時言1「戦後レジュームの子という自覚」
先日亡くなられた小田実さんは、戦後民主主義を支えたのは、一定程度の経済力を持った大多数の中流の国民であると指摘されていた。この中流は憲法が国民に保障した「教育を受ける・労働する権利」等の現象化であり、言わば憲法の子どもが民主主義の担い手として、憲法のいう「不断の努力」で形成されたという意味であろう▽この小田さんの論の内実を知悉している資本の側は、労働者的なものの無力化・社会的抹殺を策して労働力の商品化の多様化を促進し、同時にグローバリズムを口実にしての新たな収奪の段階に突進している。この新自由主義の具体的戦術は、労働者を保護して来た労働法制の規制緩和。それによって許容された多様な雇用形態の現実化。そこに惹起される労働者の分断・格差拡大の一層の促進である。教育もバウチャー制導入計画にみるように商品化の一途である。まさに権利としての教育や労働が収奪され、自由権が抑圧され、人間がより一層手段化されていく社会へと堕ちていく▽「すべての人に等しく一票を与える形式平等主義を止め、納税額に応じて票数を与えるべきだ」との声まで聞こえる今、強者(資本の側)を利する国作り、逆らう者は国の内外を問わず暴力(軍事力)で封殺する国(安倍流・美しい国)作りが「戦後レジュームからの脱却」の名の下で強行されている▽それ故今、この強行と闘うことこそ、教育・労働・自らの生活を守る闘いであり、即護憲闘争そのものである。(安保英賢)
|
|
|
|
|