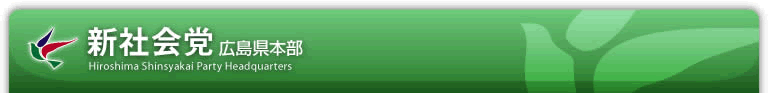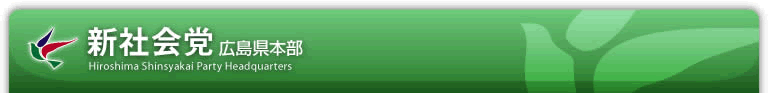|
|
|
【1月号】文楽あれこれ 6 則藤 了
|
|
2013/01/30
|
さて、やっと現代に近づいたし、歴史をたどるのがこの稿の目的ではないので、少し視点を変えよう。戦後文楽の分裂を招いた松竹ではあったが、一方、日本の誇るべき古典芸能として、赤字続きの文楽を戦後の苦しい時期、20年近きにわたって、松竹が支えてきたという功績も、見逃してはなるまい。
松竹は、明治中期以降、江戸期からの重要な古典芸能である文楽・歌舞伎、そして新興の新派を次々に買収してほとんど独占的に興行権を握り、さらには、新劇、映画にまで手を広げていった、辣腕の芸能会社である。その松竹が、映画の斜陽化による減収もあり、ついに文楽を手放さざるをえなくなった。つまり、他の儲かっている部門からの収入をもって、文楽の赤字を補填するということが不可能になったということである。これは、時代の趨勢と言っていい。言い換えれば、文楽が古典芸能である限りにおいて、経営手腕や営業努力によって何とかなるという段階を、もはや越えてしまったということに他ならない。これは、松竹が手放した昭和38年の時点において既にそうであった。
その、第一の理由は、劇の内容である。江戸期において主流たる作品は時代物であったが、そのテーマは、封建社会における義理(建前)と人情(本音)のせめぎ合いである。こんなものは、現代の若者にとっては英語以上に遠い話でしかない。さらに、現代もっぱら人気のある世話物にしたところで、ほとんどが遊女との恋愛の破綻からくる心中劇である。時代錯誤も甚だしい。そういう意味では、橋下氏の言うように、二度と見る気はしない、という見方が大勢を占めても、やむを得ないとも言える。
だが、ここで考えていただきたい。西欧の誇る歌劇にしても、内容から言えば大同小異である。日本でも人気の「椿姫」は、貴族相手の高級娼婦が、田舎出の青年貴族の純情に絆されて結婚したはいいが、男の親に自己犠牲を強いられた挙げ句病で死んでいくという話である。「蝶々夫人」にいたっては、日本の女など虫ピンで止める蝶の標本程度にしか思っていない米軍士官が、子どもまで生ませて置き去りにしたばかりか、次には妻を連れて子どもを取り上げに来るという、何ともひどい話である。内容だけを見れば、とんでもない台本である。音楽としても、20世紀のミュージカルの方がずっと耳に入りやすい。にもかかわらず、ヨーロッパの多くの地方都市(尾道・三原のように10万余の人口を有する)には必ずと言っていい程オペラハウスがあり、普段は地元歌手を中心に細々と活動を続けながら、年に数度は中央の歌手を招いて公演する。当然、赤字分は補助金で補う。これは古典と呼ばれる芸術の宿命と言っていい。勿論、欧米においても、行政は少しでも赤字を解消するため、予算を削減しようとする。が、その度毎に市民の反対運動が起こる。ただ、日本では、今回の文楽補助金削減問題のように、主として発言するのは著名な文化人であって、一般市民の動きは鈍い。
これではオペラファンの方にお叱りを受けそうである。それでもヴェルディの音楽はすばらしいし、プッチーニの音楽もすてきだ。優れた歌手とオーケストラが一体となった時、体格のいい歌手が肺結核で死んでいく女を演じて、それが何の違和感もなく真実となり、観客は涙する。それこそが芸術の力である。芝居において、あらすじは形骸でしかない。私たちが感動するのは、偏に芸の力による。
|
|
|
|
|