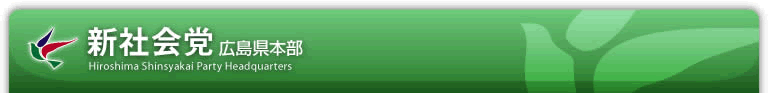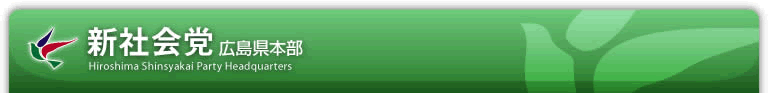|
|
|
【1月号】「昭和」史の中のある半生(9)
|
|
2013/01/30
|
「昭和」史の中のある半生 (9)
新社会党広島県本部顧問 小森 龍邦
一九四〇年(昭15)は、皇紀二千六百年だと『古事記』や『日本書紀』の伝えることを本当の史実だとして、「提灯」行列や「旗」行列をし、皇威を国民の頭に叩き込んでいる時期であった。戦時の物資不足、生活困窮が一段と進行しているにもかかわらず、 シンガポール陥落が一九四一年(昭16)二月十一日で「紀元節」に当たることから、国民を、戦意高揚の方向に舵取りする材料になった。シンガポールを陥落させるときの山下奉文司令官が、イギリス軍のパーシバル中将に無条件降伏をせまる「イエスか、ノーか」とテーブルを叩く場面がニュース映画で報じられたとき、日本国民の殆んどが、戦勝気分に酔わされたものと思われる。小学校三年生の私にして、その気分をかきたてるに十分な雰囲気であったからだ。
食糧は段々不足するようになる。成人男子一人当たり米二合四勺の配給が、いつの間にか二合一勺となり、どういう計算方法で割り出したのか知らないが、人間は「二千四百カロリー」あれば、それで活動するに十分であると聞かされていた。
その二合一勺の配給も滞るようになり、終いには、大豆から油をしぼった粕(カス)が、町内会隣保班を通じて配給されるようになる。
大本営は「臨時ニュースを申し上げます」と、「敵に甚大な打撃を与え、わが方の損害、きわめて軽微なり」と、いつもの決まり文句をラジオで流していた。
マレー半島からシンガポール攻略、そしてジャワ島あたりまで、帝国陸軍が侵攻した頃であったろうか。前号でも述べたが、私の通っていた府中東尋常高等小学校(すでにその頃は、民学校と改称していたように記憶する)四年生になったとき、学年に一個ずつ「ゴムボール」が配給され。どうしたことか、くじ運のよかった私に、学年(二百数十人)に一個の「ゴムボール」が当たった。
南方諸島から敵米英の勢力を追い出せば、このように目に見えて、物資不足は解消できるのだと、天皇制権力(当時の東条内閣)は、子どもとその保護者に教宣活動を怠らなかった。私が、この戦争は負けるかもしれないといはじめたのは、有名なマッカーサーの「アイシャル・ビー・リターン」と言って、一端はフィリピンから撤退したが、再度、フィリピンに強力な装備をもって反転してきた頃であった。
「レイテ作戦」について、当時二十円で買った雑音の入るラジオが、深夜十一時頃に五分間ぐらい流していたが、相変わらず「わが方の損害、きわめて軽微なり」の決まり文句であった。しかし、じりじりと南方諸島から後退せざるをえない状況をニュースから聞き取って、この戦争は「現に負けている」という私の分析となっていった。 それでも、昼間は学校で先生の言うことを聞いていると元気がよみがえる。夜の「レイテ作戦」をラジオで聞くと不安になるという状況であった。
五年生になると、運動場に防空壕を掘らされた。先生に引率されて、松の幼木を山から持ち帰り、それを材料にした。防空壕掘りは六年生になり、県立府中中学校に入ってからも、ずっと続いたように記憶している。
|
|
|
|
|