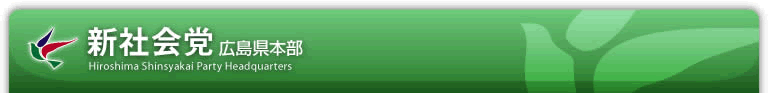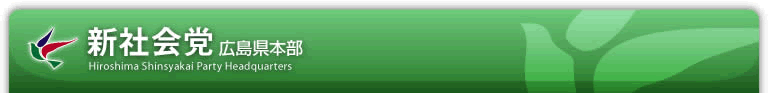|
|
|
【2月号】 文楽あれこれ 7 則藤 了
|
|
2013/02/28
|
文楽あれこれ 7 則藤 了
話を戻そう。昭和33年に発足した文楽協会は、国・大阪府・市・NHKの補助を受けて赤字を補填しながら運営を続けていくことになった。劇場は朝日座と改称された旧文楽座をそのまま松竹から借りて使う。運営も近代化して、演し物、役割などは、専門委員会(理事・有識者・技芸員代表)を中心に決められるようになる。3年後の41年には、東京に国立劇場が完成し、以後東京における文楽公演の拠点となる。
東京では、国立劇場の方針が古典の保存、埋もれた名作の発掘ということもあり、通し上演(作品の筋が通るよう、一作品の大部分を上演する)が多く行われたが、本拠地の大阪では、従来のお客の好みもあって、見取り(有名な作品のクライマックスの一段のみを幾つか並べる)方式が多くとられた。当時大阪の学生であった私などは、東京公演を見たくて歯ぎしりしたものだが、客の入りを考えると、やむを得ない面もあった。(松竹の運営する歌舞伎公演も、多くこの見取り方式を採っている。)それでも、東京でやった通し上演を大阪でやることもあり、初心者にとって分かりやすい通し上演が増えたことは評価に値する。
東京の国立劇場発足以来、大阪でも文楽を上演するための専用劇場の企画は進められていたが、土地の確保が難しく、難航していた。旧文楽座が、昔の豊竹座の位置に近く、道頓堀東詰という繁華街でもあり、好都合なのだが、松竹の同意が得られず、他を探すことになったがなかなか決まらず、ようやくのことで現在の国立文楽劇場がある千日前東、日本橋交差点東北角の位置に決まったのである。少し手狭なものの、ここなら難波からも近く、地下鉄・近鉄なども通って交通の便もよく、しかも文楽の名の基になった植村文楽軒が最初に芝居の旗揚げをした発祥の地に近く、申し分ない。昭和58年にこの国立文楽劇場が完成して、やっと文楽は大阪に本拠地を持つことができたのである。
私が文楽に通いつめた昭和40年代は、前述朝日座時代である。8代竹本綱大夫、10代豊竹若大夫らが相次いで亡くなったが、それでも、豪快4代津大夫、精緻な芸風の4代越路大夫、美声の春子大夫、南部大夫、三味線には6代鶴沢寛治、2代野沢喜左衛門、野沢松之輔、十代竹沢弥七、人形に桐竹紋十郎、吉田栄三、桐竹亀松といった名手を擁し、合同したばかりの文楽はまだまだ層は厚かった。
しかし、客の入りは悪く、平日夜の部などは気の毒なほどがらがらで、某教授から教えられて、いつも私は学割2等の切符を買って入った。2等席は客席の後方3分の1から後ろで、よく見えないのだが、どうせがら空きなのだから、最初の一幕だけ辛抱して、次の休憩に空いているいい席に移ってしまうのである。当時、2等席は学割半額で200円、大阪新歌舞伎座の歌舞伎公演の1等席2000円と比べると雲泥の差だが、それでもお客は入らない。協会側も必死で、木下順二作の新作「瓜子姫とあまんじゃく」、孫悟空の「五天竺」など、子ども向きの作品を夏休みに上演したり、7月にナイトショーとして、夜の部だけで道行など、軽い物を見せたりと、さまざまな工夫は続けられてきた。松竹の時代だってそうで、昭和30年代には、「夫婦善哉」、さらには「ハムレット」「蝶々夫人」といったものまであったと聞いている。それでも、である。
|
|
|
|
|