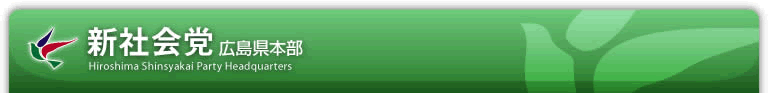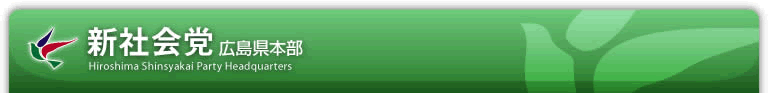|
|
|
[3月号]「昭和」史の中のある半生
|
|
2013/03/27
|
「昭和」史の中のある半生(11)
新社会党広島県本部顧問 小森 龍邦
ときたま、帝国海軍の使役から解放された日に授業が行われる。
敗戦の年の中学一年生には、もう教科書の配給はなかった。ただ「物象」(物理のこと)「国文」だけは文部省が前年ぐらいに印刷していたのであろうか、私らの手に入った。
その物象の先生が、敗戦を迎える二週間ぐらい前の授業で、「原子爆弾」の話をしてくれた。巨大なエネルギーを持っている爆弾だというのである。
「日本が、アメリカより早く開発すれば、この戦争は難なく勝てるのだが…」という話であった。
「巨大なエネルギーといっても、どのくらいの巨大さですか」と生徒のひとりが尋ねた。
「レンガ一個ぐらいの小型のものがあれば、太平洋のアメリカ航路を客船が、25年ぐらい、それを動力源として動けるぐらいだ」と、その教師は答えた。
雲をつかむような話だと、あまり気にとめていなかったが、一週間ほど後の八月六日、広島に原爆が投下された。
「新聞は、大型新爆弾でと言っているようだが…」とその教師は声を小さくして、「まさか原子爆弾ではないと思うが…」と、二、三日して、私らに語った。
広島高等師範学校卒業のこの教師の言葉から、日本の大学・高専の理科系に学んだ者は、原子力のことをすでに知っていたのかと、その後、つくづく考えさせられたということである。八月九日、長崎に原爆が投下された。 広島の原爆投下で、芦品部隊といって、空襲による火事の類焼を防ぐために道路幅を確保する(家屋の取り壊し)ために動員にかり出されていたが、多くの者が犠牲となった。
私の隣家にも、親戚を頼って、全身火傷・血まみれの人が帰ってきた。その中に無傷の少年がいた。広島第二中学校の二年生だと聞いた。二学期から私といっしょに中学校へ通う者が近所に増えたと思っていたが、一週間ぐらいして、髪の毛が全部抜け、あっという間に、その少年は死んでしまった。体験的記憶によると、傷の少なかった被爆者ほど、早く死んだと私は思っている。
八月八日の深夜、空襲警報発令の合図である役場の鐘が鳴るのが早かったか、B29の爆音の方が早かったか定かでないが、私の家から一㎞離れている府中駅の辺りから火の手が上がっているように見えた。本当は20㎞も離れた福山市街の火の手であった。
夜間は、こんなに近くに見えるものかとつくづく感じた。
早速、庭先の防空壕に避難したが、近所にこれという防空壕がなかったため、「小森の防空壕へ入ろう」と、角先で何人もの人が口々に言っているのが聞こえた。六畳間ぐらいの広さの防空壕に、土建屋のはしくれをしていたわが家はコンクリートの手練用鉄板があったので、それを二枚ほど重ねて、焼夷弾の直撃ぐらいでは破壊されないであろうと思っていたが、隣近所の人が、こんなに詰めかけたのでは、蒸し焼きになってしまうことが心配になった。「逃げよう」と一番奥から私は叫んだ。詰めかけてきた人びとは、いっせいに逃げなければという心理にまとまった。照明弾の投下によって、周囲は真昼間のようであった。
|
|
|
|
|